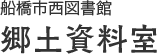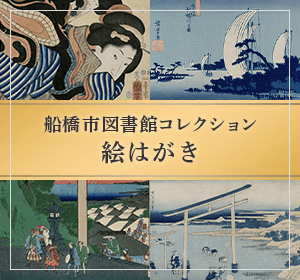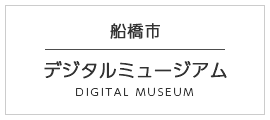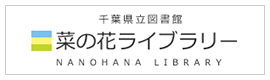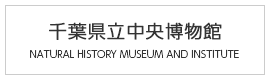宿場町船橋の沿革
宿場とは?
宿場とは何か。宿屋がある場所というのでは、3分の1しか正解ではない。宿場は旅人が泊まる旅籠があるから宿場というだけでなく、きちんとした公的業務をになっていた場所である。
その第一は公用人馬の継立(つぎたて)で、次の宿場まで公用旅行者と荷物を運ぶのである。だから宿場では、常に馬と人足を用意して置かねばならない。その上で人馬に余裕があれば、有料で一般旅行者の需要にも応じた。第二は冒頭で記したように、旅行者を宿泊させることである。これも公用旅行者が最優先で、少し大きな宿場には本陣という武士・公家・高僧等の宿泊する旅館があった。第三は通信の業務である。これも公用文書が優先で、次の宿場まで早く確実に届けなければならないから、健脚の飛脚人足を待機させて置く必要があった。
それらの業務の指揮をとるのは宿(しゅく)役人であり、長を問屋といい、場所は問屋場といった。地方では村役人が宿役人を兼ねる場合もあった。実務をするのは事務担当の帳付(ちょうづけ・書記)と、人馬を振り分ける人馬指(じんばさし)で、問屋から雇われていた。
公用の旅行者・公家・高僧等が旅をする場合は、前もって伝馬役所へ届けると、役所から用務・必要な人馬数・日時を記した証文を各宿場へ出す。宿場ではそれにしたがって人馬を用意する。多数の人馬が必要な時は、近隣の助郷村に割り当てた。助郷は制度化されていて、助郷村々はたとえ農繁期でも、指定の人馬提供を拒否できない建前であったが、時には両者間で訴訟沙汰となる場合もあった。
「船橋宿」の概要
江戸時代の「船橋宿」というのは、五日市村・九日市村・海神村3村の総称であった。この3村は共同で人馬継立等の業務にあたったが、実際の業務は五日市村と九日市村・海神村の2手に分かれ、業務を分担してつとめ、大がかりな御用の時は一緒につとめたようである。
船橋の次の宿場(継立場)は佐倉道が八幡と大和田、上総道は馬加(幕張)、御成道は犢橋、行徳道は行徳であった。しかし周知のように、船橋宿の中心は慶応4年(1868)の戊辰戦争の兵火で焼失させられてしまったので、宿場関係史料はほとんど残っていない。特に問屋業務の史料は皆無に等しい。わずかに残る古文書や地誌から、次のようなことが知られるのみである。
船橋宿には寛政12年(1800)に、22軒の旅籠と1軒の本陣があった。旅籠数は天保年間(1830年代)には29軒に増加し、明治初期まで同数であった。ただし旅籠は九日市村住民で、「株」を有する者のみが営業することを許されていた。
弘化元年(1844)と推定される古文書「乍恐舟橋宿と唱度趣意左ニ奉申上候」によれば、船橋宿では人足15人と馬15頭を用意して置き、大がかりな御用の時は助郷村々へ割り当てた。
問屋場は五日市・九日市に各1ヶ所あった。五日市は海老川河畔の街道北側(宮本1-22)、九日市は東魁楼西側(本町4-36)の場所であった。
「船橋宿」あれこれ
船橋は佐倉道(成田街道)最大の宿場であり、交通量・旅籠の利用者とも多かったが、佐倉道は道中奉行の管轄が八幡宿までであったので、前記古文書名から知られるように、正式には「船橋宿」と名乗ることができず、公的文書には「船橋村」と記していた。つまり船橋は、当時の呼び方では、継場(つぎば)とか継立場と称される場所で、制度上は「宿(しゅく)」ではなかった。しかし、紀行文や私的な記録類には、ほとんど「船橋宿」と書かれている。
船橋宿で最も有名なのは飯盛女(宿場遊女)の「八兵衛」であった。八兵衛の名は言動が粗野だからついたといい、川柳に度々詠まれ、十返舎一九の作品にも登場するほど名物扱いされた存在であった。
江戸時代の宿場は、一般の農村から比べると賑やかな場所で、だから歓楽街的要素も多分にあった。船橋はその一面を近代に入っても持ち続けた。貸座敷業という名目の旅館がそれである。
明治以後の変遷
明治27年(1894)に総武鉄道が開通し、30年に本所(錦糸町)~成田が鉄道1本でつながると、船橋は宿場としての機能を徐々に失っていく。明治後期から習志野原の軍隊が拡充されると、貸座敷業はやや持ち直すが、町全体としては宿場から地方商業都市へと転換を遂げていった。
その後、大正10年(1921)に娼妓を有する業者を1ヶ所に集中するよう県から通達があり、やがて昭和3年(1928)に、九日市と海神の入会地に新地遊廓が誕生した。この時、現本町通りの業者はほとんど廃業し、新地の経営者は東京等の業者が占めた。元々の宿場の通り(本町通り)には、数軒の割烹旅館が存続したのみであった。