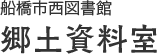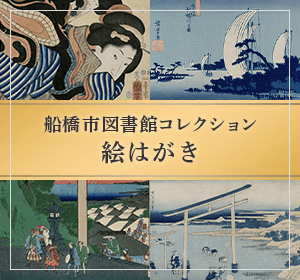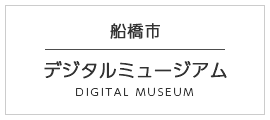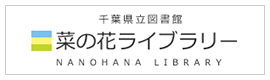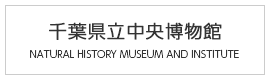市域の埋め立て
1 初期の埋め立て
船橋市域における海面の埋め立ては昭和20年代からのものがよく知られているが、小規模な埋め立ては10年代にも行われた。『昭和十六年 船橋市事務報告』には、17年2月付の市長の巻頭文として「本市多年ノ懸案タル湊町地先海面ノ埋立並二船溜設置ハ漸ク其手続きヲ完了シ近ク着工ノ運ビトナリタルハ真二御同慶ニ堪エザル所」とあり、18年の事務報告には、4月23日付で市議会に「公有地埋立地ニ町名ヲ付スルノ件」が諮問されているので、おそらく17年度中に埋め立てが完了したものとみられる。同事務報告によれば、場所及び面積等は下記の通りである。
「五、公有水面埋立工事
埋立ノ場所及面積 船橋市湊町一丁目、二丁目、三丁目、地先(海面)五万四千三百二十四平方米
内訳
道路 八千七十七平方米
荷揚場 二千七百七十平方米
利用地 四万三千四百七十七平方米
利用地中一、二三七坪四合八勺売却此代金六万参千六百弐拾六円参拾八銭平均五拾弐円拾銭也 猶 船溜追加工事防波堤補強工事埋立地地下水工事等ハ目下着々準備中ナリ」
この埋立地は現在の湊町小学校周辺の場所である。
※『船橋市史 現代篇 上』の巻末の「参考資料」24ページ「初期の埋立事業」には「昭和九年六月、船橋町漁業組合が企業体となり、船橋町の航路を三〇間及び二〇間幅で延長二、三九〇間の浚渫計画をした。工費は二八万円で、浚渫土量をもつて、大丸(湊町四丁目塩田跡)、都疎浜、三田浜(塩田跡)競馬場という所の埋立が行われた。業者は、臨海工業株式会社であった。
昭和一五年、市の企業として学校敷地造成のため、漁業組合の同意を得て、船溜り造成によって得る浚渫土量で二万坪の埋立が行われた(現湊町小学校敷地一帯)。業者は、臨海工業株式会社であった。」とある。
2 戦後の埋め立て
(1)11万坪の埋め立て
戦後の経済低迷期に、その打開と産業の興隆をめざして東京湾の埋め立て計画が打ち出された。千葉県側では船橋市が他に先駆けて埋め立て事業に乗り出した。発端は昭和23年8月26日付をもって、当時の市長松本栄一より船橋市漁業会長宛に、起業埋立工事に伴い、漁業会が漁業権を有する公有水面を11万坪埋め立てさせて貰いたい旨の申し入れを行ったことに始まる。漁業会は同意の条件として、漁業権の補償として1万坪を譲渡すること。埋立工事を中止する場合は埋立地の1割を無償譲渡すること。工事完了後に無償譲渡地の隣接地1万坪を漁民に原価で払い下げること等を提示し、24年2月に合意に至った。その直後に市長は公有水面11万坪埋立工事計画を立案し、県知事の認可を得た。
『ふなばし市政の概要 ‘75』には次のようにある。
「昭和23年に(中略)宮本町1丁目105番地より同2丁目185番地に至る地先、380,373m2(115,263坪)にはじまる。これは船橋港が指定港湾となった結果、当時の船溜りの南側にさらに商港を建設することとなり、航路幅員拡張と延長のための浚渫土砂の捨場として計画されたものである。(中略)同年度施行の第1期工事8,417坪が工事費10,200千円をもって随意契約が昭和24年2月に東亜港湾工業株式会社と締結された。この第1期工事は護岸工事を残して埋立てられ、その後起債の関係で工事中断のまま日時が経過した。」
そのように埋め立て工事が着手され、25年2月に8,417坪が竣工した状態で中断されていた。その転機となるのは26~27年の天然ガスの試掘によって船橋の海岸から低地一帯に、相当量の天然ガスが埋蔵されていることが確認されたことであった。そこで、当時の高木市長はその開発権を民間企業に与え、見返りとして資金援助を得て埋め立てを再開して企業を誘致し、市財源の増大を計画した。
その市長の呼び掛けに応じた財界の有力者によって、27年7月に社団法人船橋ヘルスセンターが設立された。
同年8月、市はセンターと天然ガスの譲渡、それを利用した温泉の使用権の譲渡、埋立工事委託に関しての契約を締結した。契約の内容を抄出すると下記のようである。
ー、市は中断状態の八四〇〇坪埋立を完成させ、実費でセンターに譲渡する(一条・二条)
ー、市は天然ガスを一立方米六円でセンターに譲渡し、湧出する温泉の使用権を無償で譲渡する(四条)
ー、センターは市の埋立計画の残り部分を自己資金で施行完成し、市はそれを無償でセンターに譲渡する(八条)
船橋ヘルスセンターは公益法人であったので、営利事業を行う会社として朝日土地興行株式会社が28年2月に設立され、両者間で契約が締結されて埋め立ては会社によって実施された。すでにほぼ埋め立てが終了していた8千坪の部分は29年6月に完成してセンターに譲渡され(市城編入面積は7,526坪に変更されている)、そこに30年に温泉の船橋ヘルスセンターが建設され、11月に営業を開始した。
これより先昭和27年10月、市は県知事宛に工事期限の延長願いを出していたが、第2期・第3期工事については28年7月・10月に申請書を提出し、県からは29年6月に改訂命令書が下付され、次のように変更された。
第一期(旧第二期分)三九,二一六坪余は三十年十二月三十一日
第二期(旧第三期分)七五,〇六六坪余は三十一年十二月三十一日
までに竣工すること。
ところが29年9月には設計変更の必要を生じて申請し直し、30年3月に許可となった。内容は面積の訂正であった。
その間にも工事は進められており、埋め立ては急ピッチで行われたらしく、29年末には埋め立てはほぼ完了していたようである。(丹沢善利著『自照』には「二十九年末、ついに十一万坪の埋立てを完了いたしました。」とある)。
しかし、行政的には新1期分(北側)34,391坪は30年12月に市域に編入され(現浜町1丁目部分)、新2期分(南側)の75,222坪は31年8月に編入されている(現浜町2丁目)。
(2)50万坪埋め立て
前記の埋め立てが行われている時期に、併行して50万坪の埋め立てが計画された。昭和28年8月船橋漁業組合総代協議会に当時の高木市長が出席し、埋め立ての事前説明と協力要請を行った。大規模埋め立ての先駆けとなる行動であった。この埋め立て構想は東京湾沿岸を一大工業地帯にしようとする国・県の政策と、増大する財政需要に対処するために企業誘致をするには大規模な埋立地の造成が必要との船橋市の立場が一致しての計画である。そして大規模な埋め立てを実施するには、漁場を失う漁民の了解を得る必要があるので市長の要請となったものである。
29年10月に市長から漁業組合長宛に協議依頼が出されたが、組合内では反対や慎重論も多く何度も内部の協議が重ねられた。また、市と組合間で補償の条件についての協議も行われた。そして同年12月に組合幹部との間に了解が成立し、下記のような条件で仮同意書が結ばれた。
一、補償として七万五千坪を組合へ譲渡する。
一、現金補償として二千五百万円を組合へ提供する。
一、漁業振興事業補助費として、三十年九月末日までに二千五百万円、三十五年九月末日までに二千五百万円を組合へ交付する。
一、組合法による総会決議により決定の場合は、改めて本条件を締結する。
これにより、県の埋立許可を得る関係から30年3月、県側(知事外7名)、市側(市長外4名)、朝日土地側(社長外2名)による審議が行われ、船橋市が企業体となって朝日土地に埋立権を譲渡して実施するという結論になった。それからすぐ設計に着手して6月に市長から知事宛に埋立免許の出願をした。その内容を抄出すると
面積
第一期 一六ニ,八九一坪(利用地・荷揚場・道路の合計)
第二期 一一四,〇五〇年(同上)
第三期 二二三,〇五九坪(同上)
竣工期間
第一期 昭和三十二年十二月三十一日
第二期 昭和三十三年十二月三十一日
第三期 昭和三十四年十二月三十一日
埋め立ての費用
一二億円
それに対してすぐ許可は出ず、30年9月に知事から市長宛に「再調の上提出」するよう指示があった。その内容は、埋め立ての目的を詳しく記載すること(工場敷地・住宅地等)や、費用の明細書を詳細にする等14項目にわたるものであった。
また、漁業協同組合での補償問題は難航し、30年8月及び31年6月の総会は流会となり、組合内は賛成派・反対派に分裂してしまった。その後、賛成派漁民によって期成同盟会が作られ、市・市議会も説得と折衝にあたった結果、31年8月の総会で結論が得られ、同年10月に細目協定が結ばれた。
その結果、31年11月に千葉県知事柴田等から船橋市に対して、公有水面埋立を免許するについての「命令書」が出された。その中では「第二条 公有水面埋立の目的は京葉工業地帯の一環として工場用地を造成し、工場敷地に供するものとする」や第5条の道路敷26,223坪と荷揚場敷地11,782坪は「県に帰属し公共の用に供すること」とあるのが注目される。
翌月に埋め立ての起工式が行われ、工事が始まったが完成期日は当初計画より遅れ、下の通りであった。
第一期分 昭和三十五年七月 一六九七四五坪(現日の出町一・二丁目)
第二期分 昭和三十五年七月 一一五五〇三坪(現栄町)
第三期分 昭和三十六年一二月 二三七四〇八坪(現西浦町)※一月・一一月・一二月に分割完成
(3)11万5千坪の土取り
この場所は(1)の埋立地の北西側にあたり、通称「遠藤浜」「松遠新田」と呼ばれ、明治時代に開かれた塩田の跡であり、私有地で公有水面ではなかった。塩田時代の堤防が大方失われ、昭和30年代には満潮時には海面下になる状態であった。『船橋市史 現代篇 上』には「市及び組合に対しそのための土取場、補償等のことで交渉があり、数次折衝の結果私有地代表の木村栄吉から旭土地株式会社長(※朝日土地興行株式会社の誤り)丹沢善利との間に譲渡の契約が成立し」とあるように、50万坪の埋め立てと併行して埋め立てられた(現栄町1丁目)。
(4)18万坪埋め立て(ヘルスセンター前面)
千葉県によって船橋港への航路を掘り下げる浚渫工事によって生じる土砂の処分場として計画されたのがこの場所である。ヘルスセンター前面(南側)埋立地である。昭和37年10月に市議会に対し諮問があり、11月に了解の答申をした。翌38年6月千葉県の施工により着工され、40年3月に17,069坪が竣工し、同年12月に8,289坪が竣工した(現若松町)。埋め立ての事業者は朝日土地興行であった。
(5)昭和40年代の大規模埋め立て
昭和30年代後半から40年代にかけ、産業・経済の急速な発展に伴い、東京湾に出入りする船舶の貨物量は増大の一途をたどった。これには湾岸に造成された工業地帯の需要だけではなく、商品の輸送需要も加わっていた。
そのため千葉県では、京葉工業地帯の西の拠点である葛南(船橋・市川・習志野等)の中心港湾として、通称京葉港(後に千葉港葛南船橋・市川・習志野港区)の建設計画を打ち出した。
それに伴う公有水面埋め立てについては、41年・42年に県から船橋市議会に計画案の説明がなされた。
また建設の前提となる漁民の漁業補償問題については、県が漁業協同組合と交渉を重ね、44年3月に交渉が妥結した。同月、知事から市議会に対して埋め立ての可否について諮問があり、市議会は異義ない旨答申した。
埋め立ては西側部分が先に44年7月に認可され、49年10月に竣工した。面積は402,325坪である(現潮見町)。
東側部分は44年11月に認可され、若松2丁目西側の部分は47年6月竣工した(面積20,371坪・現浜町2丁目の一部)。若松2丁目南側の部分は50年1月に竣工した(面積87,174坪・現浜町3丁目と若松3丁目)。さらに、その南側の広大な部分も50年1月に竣工した(面積377,108坪・現高瀬町)。
続いて、その北東側は46年6月に認可され、52年3月に竣工した(面積115,581坪・現高瀬町)。
その他にも埋め立て地の間や、縁辺の小規模な埋め立ては昭和20年代から60年代まで何度も行われた。それらを合わせると、船橋市域の埋め立ての総面積はおよそ200万坪に達する。